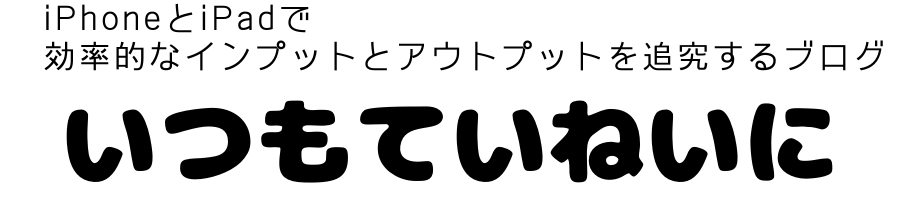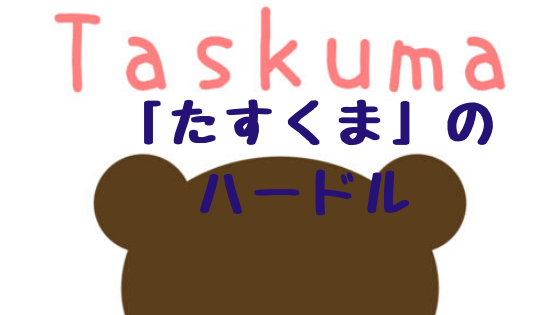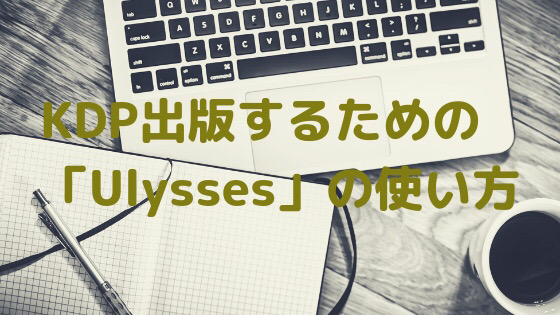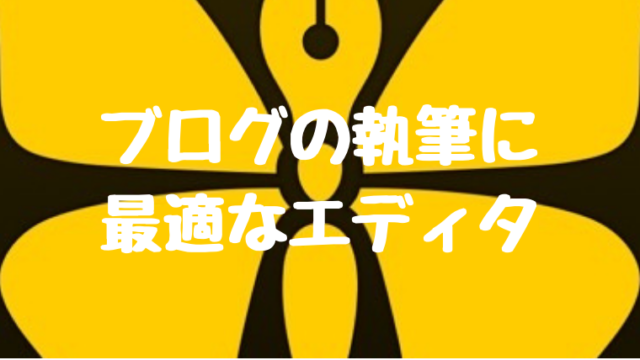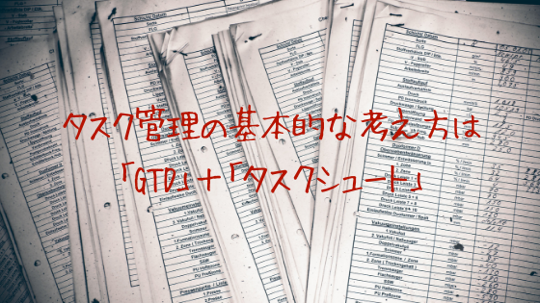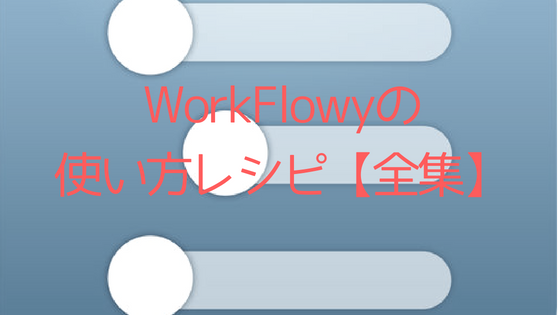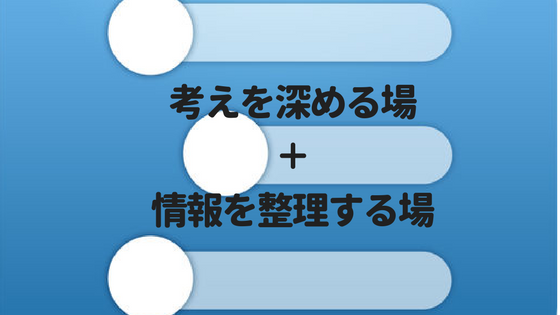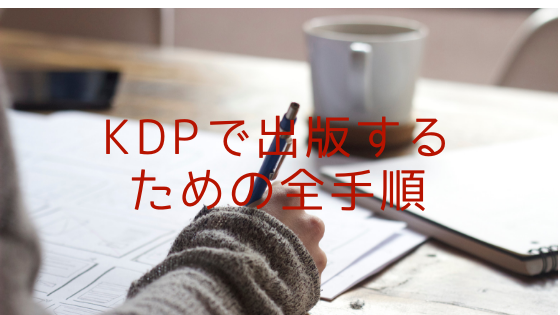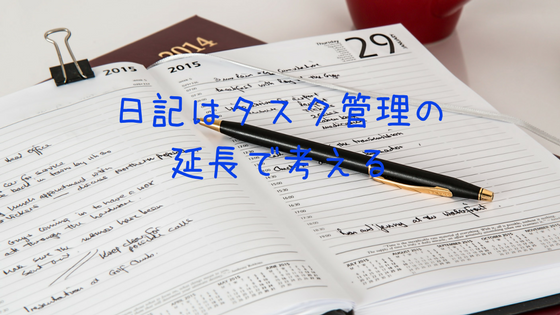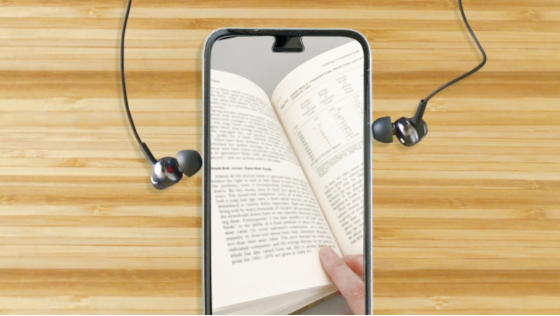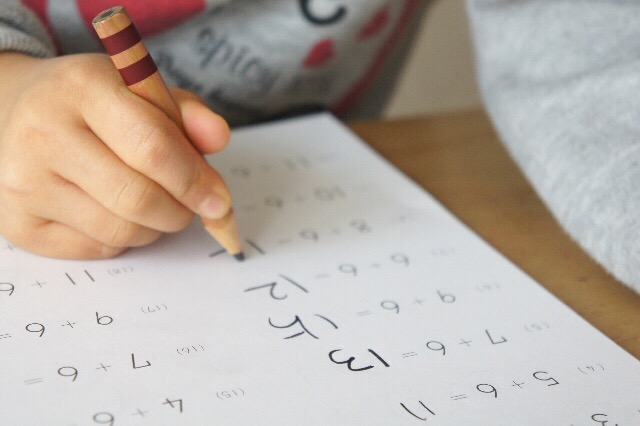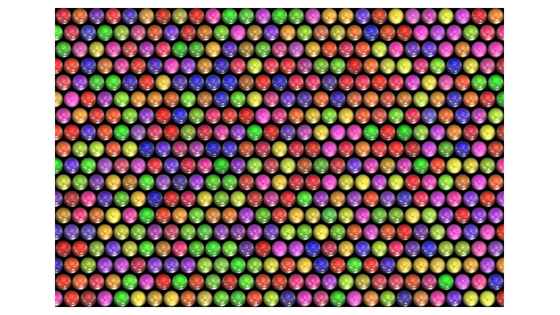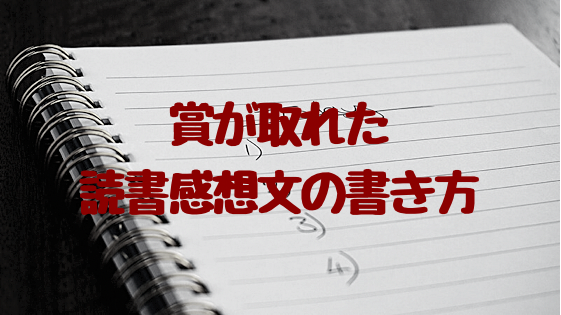子どもを読書好きにしたい、と思う親御さんは多いと思います。
ウチも、今、小学校2年生の息子と保育園の子どもがいますが、読書好きになってもらいたくて、いろいろ試行錯誤しています。
その甲斐があってなのか、上の息子も下の娘も、暇さえあると絵本を開いて自分で読んだり、親に読み聞かせをせがんだり、だんだん絵本を読むことが好きになっていきました。
しかし、上の息子は小学校に上がって少し経ったあたりから、徐々に本を読む習慣がなくなってしまいました。
そのとき、改めて、子どもを読書好きにするにはどうしたらよいか、と考え、自分の中で1つの結論が出ました。
それは、幼児期と小学校に上がってからでは、子どもに対する親の働きかけを変えなければいけない場合がある、ということです。
では、どう変えなければいけないのか。それを本記事では考えてみたいと思います。
1. 小学生の子どもを本好きにするために私が考えたこと
上の息子が1歳半のとき、絵本の読み聞かせを始めました。3歳から配本サービスを利用して、月1冊送られてくる絵本の読み聞かせを毎晩していました。また、それに加え、月1、2回、本屋や図書館へ行き、息子が読みたい、という本を買い与えたり、借りたりしていました。
その取り組みがよかったのか、結果的に本をよく読むようになったのですが、前述のとおり、小学校1年生の後半あたりから本をあまり読まなくなってしまいました。本屋や図書館へ行っても、「読みたい本はない」と言うし、毎晩していた読み聞かせは、もういい、と言うのです。
(1) 本を読まなくなった原因を考える
よく本を読んでいた息子が小学校になってからあまり読まなくなったのはどうしてだろうか。
まずは、本をあまり読まなくなった原因をいろいろと思いつく限り考えてみました。
- 宿題など小学校になっていろいろやるべきことが増えたから。
- 興味のあるテレビ番組が増え、本よりも他に興味を引くものが多くなったから。
- 小学校低学年を対象とした本は文字量やページ数が多くて読むのが大変だから。
他にも、カードゲームにはまったため本よりもカードゲームに時間を使いたいから、本を1回読んだら内容を理解できるようになったので何度も読む必要がないから、など、まだまだ考えられる理由がありますが、決定的な理由として、私はこう考えています。
他の何をするよりも優先して読みたくなる本と出会えていない、ということです。
どうしても読みたい内容の本であれば、文字量が多かろうが、忙しかろうが、他にやりたいことがあろうが、何よりも優先させて本を読むはずです。
その何よりも優先させて読みたくなるような「おもしろいと思える本」と出会う機会が減っている、ということではないか、と思うのです。
(2) 名作とエンターテイメントのバランスを考える
私が息子のために絵本を選ぶときは、年齢別にオススメの本を紹介する本や雑誌、サイトなどを参考にしていました。さらに月1冊の配本サービスを利用していました。紹介されている本や配本される本はすべて名作揃いの素晴らしい本ばかりだと思います。
ただ、再び、子どもの読書欲を高めたい、と思っている今は、必ずしもそれらの名作がよい影響を与えてくれるわけではない、と考えるようになりました。
いわゆる名作とよばれる本は、昔から長年にわたって読み継がれ、大人にとっても示唆深く知的なおもしろさのある、素晴らしいものが多いと思います。ただ、子どもにとっては面白味に欠ける名作もたくさんあると思うのです。
ここで言う面白みとは、小学校低学年にとっての面白味です。具体的には、笑えるようなギャグ的な要素だったり、エンターテイメント的な要素だったり、際立ったヒーローキャラが登場したり、といったところでしょうか。
大人だって名作といわれる本よりも大衆文学を好んで読む人の方が多い、という言い方は少し極端かもしれませんが、少なくとも私は、評価の高い純文学などの名作よりも、大衆文学とよばれるようなエンターテイメント要素の高い本の方が、おもしろいと思ってしまいます。
子どもに名作を読ませる必要がない、ということを言いたいわけではありません。名作もエンターテイメント的な本もどちらも大切で、バランスなんだとは思います。ただ、再び、本に目を向けさせたい、と、思っている今は、小学校低学年の子どもがおもしろいと思える本と、たくさん出会わせてあげて、本を読むことの楽しさを伝えていきたいのです。
2. 小学生の子どもを本好きにするための2つのアプローチ
幼児期は、前述したように、名作を中心とした親が選んだ絵本を与えたり、子どもに選ばせたり、配本サービスを利用したりして、毎晩、絵本の読み聞かせをしていました。
小学校2年生の息子には、そのアプローチを少しだけ変えてみることにしました。
(1) 名作にこだわらず、子どもが読みたくなる「おもしろい本」を与える
小学校低学年がおもしろいと思える本、というのは、どんな本なのか。親としては、おもしろいに加え、小学校低学年のレベルに応じた文字量もあってほしいところです。漫画や絵ばかりの絵本、というのも避けたいのが本音です。
さらに欲を言えば、その都度、こういったおもしろい本を探すのは大変なので、シリーズものだとありがたい、という気持ちもあります。
こういったおもしろい、かつ、文字量が小学校低学年レベル、さらにシリーズものだと尚よい、といった本を探すのは、実際に探してみると、なかなか難しい問題でした。
でも、ウチでは、そういった本を探しあて、息子に与えたところ、本への興味を取り戻したのかどうかはわかりませんが、少なくとも与えた本は、真剣になって読み進め、何度も読み返していました。
このアプローチは功を奏したんだと思います。
では、どんな本を子どもに与えたのか。それは、以下の記事で紹介していますので、そちらを参照してください。本記事では、もう1つのアプローチを次に紹介したいと思います。

(2) 子どもが興味を持ったテーマを発見したら関連した本をすぐに与える
最近、息子は、テレビアニメ「妖怪ウオッチ」で「三国志」をベースにした話が放映されたことに影響され、三国志について、いろいろ聞いてくるようになりました。これはチャンスだと思いました。
小学校低学年でも読める「三国志」の本をすぐに買い与えたのです。
2年生では少し難しいかなとも思える本ではあったのですが、難しい言葉があると私に聞きながら、暇さえあると、本を開いて真剣な様子で読んでいます。
5冊シリーズの本なのですが、あっという間に読み終え、私に三国志に関する問題を出してくるほどになりました。
実は、息子が保育園のときにも同じようなアプローチをしたことがあります。同じく「妖怪ウオッチ」の影響で「西遊記」に興味を持ったときには、すかさず「西遊記」の本を与えたり、数字に興味を持ったときには「数字」に関する絵本を与えたり、興味を持ったテーマを察知したら、すかさずそのテーマに関連した本を与えていました。
そういった本は、必ずと言っていいほど、読みふけります。内容の吸収度も驚くほど早いです。多少、難しい内容であっても、がんばって理解しようとしますし、わからなければ親に聞いてきます。読むのを諦めるということはありませんでした。
親としては、日頃からアンテナを高くし、子どもの興味のあるテーマを察知したらタイミングを逃さず、すぐに関連した本を与えることが大切だと思います。
ちなみに、どんな本を与えたかというのは、以下の記事で紹介していますので、こちらを参照してください。

3.おわりに
他にも、家族で読書の時間を決めたり、親が読書をしている姿を積極的に見せたり、といったこともしてみましたが、一番効果のあったアプローチが上の2つでした。
ちなみに、配本サービスは今も続けていて、届くとすぐに読み聞かせをしています。ただ、それっきり自分では読もうとはしませんので、少しもったいない気がしないでもないですが、名作に触れる機会としてとらえ、まあいいかな、と思っています。
この記事は以上です。
もし、少しでも参考になった内容があれば、下の「いいね」ボタンを押してください。励みになります!
このブログには、iPhone・iPad・Apple Watch、アプリ、Kindle出版、ブログ運営などに関する記事があります。カテゴリーページや下にある「関連記事」を、ぜひご覧ください。